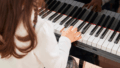表現すること
「表現する」とは、どんな意味があるのでしょうか?
生徒さんのレッスンをはじめ、コンクールの審査やリハーサル等で演奏を聴かせて頂くなか、「表現するとはなんだろう?」と考えることが多くあります。
レッスンを受けていると、「もっと表現して」「どんなイメージで表現したい?」など、先生から言われたことは少なからずあるかと思います。
改めて『表現する』とはどんな意味があるのでしょうか?
クラシック音楽の歴史において非常に重要なイタリアは音楽の発祥地の一つですが、
言葉からどう派生しているか考えて見ると気づきがあります。
言葉から考えて見ると発見が!
多くの音楽用語はイタリア語ですし、音楽のフレーズや構成など、イタリア語と密接に繋がっています。
そこで、語学を少しだけでも知っておくと大きなヒントとなります!
イタリア語では演奏することに対して、
「esprimere」
「interpretare」
「eseguire」
「suonare」
などが使われますが、どれも微妙にニュアンスが違うのです。
今回は、「表現する」という言葉を日本とイタリアでの文化的背景・語源から見つめ直し、意味の違いを考えてみたいと思います。
【1】イタリア語で「表現する」とは?
イタリア語で「表現する」は主に:
-
esprimere(エスプリーメレ)
-
interpretare(インテルプレターレ)
が使われます。
特に、esprimereが「表現する」という意味で使われているのですが、
語源から考えてみると「なるほど!」と気づきがあります。
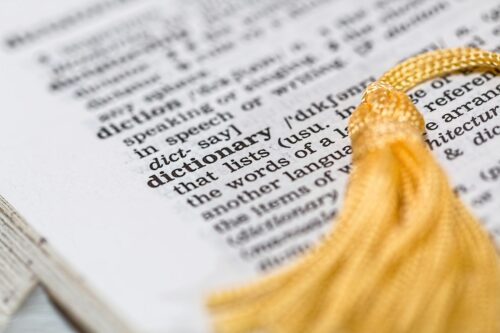
● esprimere の意味と語源
「esprimere」は、ラテン語の exprimere(ex=外へ+premere=押し出す)が語源で、
「内にあるものを外へ押し出す」というイメージがあります。
つまり、「心の中にある感情や思考を、外に出す」こと。能動的な動きです。
恥ずかしいという思いや、失敗したらどうしよう、緊張して内に縮こまってしまうこともあると思いますが、ヨーロッパでは表現を表に出すことが、その人の存在価値を知ってもらうために大切だ感じる場面がよくあります。
ヨーロッパでレッスンを受けていると、言葉にならない想いや、内に秘めた感情、情熱を自分が思っているより大袈裟に出しても、「足りない!」と言われることが多々。
表現することを恥ずかしがらず、怖がらず、思いっきり外に放出してみて下さい。
やり過ぎて度を越してしまった時、先生や助言して下さる方が教えてくれるはずです!
● interpretare の意味と使い方
一方で「interpretare」は、「解釈する」「演じる」「翻訳する」といった意味を含みます。
音楽の場合、作曲家の意図を読み取り、自分の解釈で演奏することを「interpretare」と言います。
つまり「interpretare」は「作品の意味を読み解き、再構築すること」。
創造性と読解力が必要とされる表現ですね。
イタリアで驚いたのは、感情的なイタリア人が、まるで大きな建物を構築する様に、細かく楽曲分析をしていることでした。
正に職人気質。細かい練習をしながらも、分析力が鋭く、細部までこだわった解釈を語ってくれた友人達、先生方を思い出します。
【2】日本語の「表現する」の語源と成り立ち
日本語の「表現」は、漢語の組み合わせで:
-
表(おもて)=見えるもの・外側
-
現(あらわす)=明らかにする・姿を見せる
つまり「見えない内面を、外に見える形で示すこと」という意味になります。
こちらも「内面を外へ出す」という点では esprimere に近いですが、
どちらかというと自発的というより、自然と滲み出るものというニュアンスもあります。
私は日本の伝統芸能が大好きで、歌舞伎や舞踊をよく観劇するのですが、ヨーロッパとは全く違う空気感を感じながら少しだけでも世界観を理解できたとき、「日本人で良かった!」と思う瞬間があります。
日本人は繊細で独特な空気感、静けさ、無を表現するのが得意な人種な気がします。「間」の取り方や、滲み出てくる美しさ、所作。
クラシック音楽の表現とは全く違う世界ですが、邦人の方の曲を演奏する時に、こちらの表現方法が個人的にはしっくりくることがあります。
レッスンの時に感じたこと
「表現する」ことについて具体的な語源など、聞き慣れない語学のお話は少し難しい話題ですが、最後にレッスンをしながら気づいたことを書いて終えたいと思います。
熱心にレッスンに通ってくれている小学生の生徒さんは、学校のクラブで「ディベート」があるそうです。
人前で意見を言うこと、発表するスキル、自己表現を磨くために入っているそうなのですが、レッスンの時も曲をイメージをする感性が素晴らしく、物語や色彩、どんな風景が広がっているか、様々な情景と表現を話してくれたり、描いて見せてくれるのです!
その生徒さんのお話を聞くことが大好きで、曲のイメージが私の内にも広がっていく感覚があり、いつも楽しみにしています!
生まれ持った感受性もあると思うのですが、とても音楽的で表現力があり、様々な経験が音楽にも活かされていることに納得ですし、音楽と日頃の生活、経験が全て密接に繋がっていることも改めて納得しました。
「練習する」ことはピアノの向上に必須ですが、毎日ただお部屋にこもって何時間もピアノを弾いていても感情表現は豊かにならないと思います。
音楽も音を通じたコミュニケーションなので、普段の人との接し方なども音に現れますし、表現力にも通じてきます。
子供の頃は感受性が敏感で、何もかもが新鮮で素直に受け入れる感性を持っているので、その大切な時期に多くの経験をしてほしいと思います。

【結び】
「何を表現したいのか」「どのように表現するのか」を問い続けること。
それは演奏者として、また一人の人間として大切な気がしています。
しかし、音楽は一つのエレメントではなく、表現だけで完結しないということは追記しておきたいと思います。
私の大尊敬する音楽家、ダニエル・バレンボイムのマスタークラスの動画は有名で、DVDを何度も何度も繰り返し観ているのですが、「全てはつねに永久に繋がっている」と語っています。
素晴らしい動画なので、是非観て下さい♪
⇨ Baremboim talks about music 音楽について
⇨ こちらは同じくダニエル・バレンボイムの動画「音楽の聴き方」